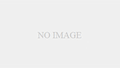タラちゃんが交通事故で亡くなり、一年が経っていた。
今だに姉さんはショックから立ち直れないでいる。
だけど傍から見れば以前となんら変わりのない元気な姉に見えるだろう。
それは、姉さんの中では全てが以前のままだからだ。
サザエ「なに言ってるのよカツオ、タラちゃんならここにいるじゃない」
ボロボロになった縫いぐるみを抱いた姉は、それを我が子だと信じているのだった。
カツオ「何言ってるんだよ姉さん、しっかりしてよ……」
サザエ「私はしっかりしてるじゃない、あんたこそ顔色悪いわよ、ねえタラちゃん」
姉さんは同意を求めるように腕の中の縫いぐるみに微笑みかける。
もちろん縫いぐるみは何も答えない。
サザエ「今日の夕飯はハンバーグにしようかしら、カツオが元気になるように」
カツオ「わ、わーい……やったー」
サザエ「タラちゃんも好きよね、ハンバーグ」
もちろん縫いぐるみは何も答えない。
サザエ「カツオ、私は夕飯の支度をするからあんたはタラちゃんと遊んでてくれる?」
カツオ「わかった……じゃあ、あっちで遊ぼうか、タラちゃん」
僕は姉さんから縫いぐるみを受け取る。
抱き抱えるとだらりと四肢が垂れた。
僕はそれを持って自分の部屋へと向かう。
とても姉さんの視線が届くところにはいられなかった。
カツオ「ワカメ……ここにいたんだ」
ワカメ「うん、……あ」
ワカメは振り向き僕の手にある縫いぐるみに視線を向けると、僅かに表情を強張らせた。
縫いぐるみを息子だと思い込む姉について、どう思っているのか話合ったことはない。
しかし、一時期のふさぎ込んだ姉さんの姿よりは今の方がよいのでは、と考えているのは同じだろう。
ワカメ「お兄ちゃん、それ……」
カツオ「ああ、姉さんがタラちゃんと遊んでろってさ」
ワカメ「ちょっと貸して」
カツオ「え?」
ワカメ「ここ、ほつれてきてるわ、直さないと……」
縫いぐるみは姉さんが四六時中連れ回しているせいか、ずいぶんとボロボロになっていた。
男の子の形を模したその縫いぐるみは、タラちゃんに似ていたからつい、と父さんが買ってきたものである。
タラちゃんが死んでから一ヶ月程経った頃のことだった。
皆はそれを見せたら姉さんがタラちゃんを思い出してよけいに悲しむのではないか、と懸念していたが、事態は予想外の方向へ向かった。
サザエ『あら、タラちゃん!こんな所にいたのね』
仏壇の近くに置いていたその縫いぐるみを、姉さんが明るい声を出しながら抱き上げたのだった。
久しぶりに見る姉さんの笑顔に、家族は皆喜んだ。
タラちゃんを失った悲しみは癒えはしないだろうけど、しばらくはこの縫いぐるみで気を紛らわせるのではないかと思った。
一日中暗い部屋に篭り、ろくに食事もとれないような生活になっていた姉さんは、その日から変わった。
いや、元の姉さんに戻ったのだ。
タラちゃんという存在が欠け、崩れていたバランスが縫いぐるみによって埋められたからである。
姉さんは縫いぐるみにタラちゃん、と呼びかけまるで本当の子供のように接した。
皆、始めの頃はそれを暖かく見守っているだけだったけど、それが一月経ち、二月経ち、
変わらず縫いぐるみを可愛がり続ける姉さんが、さすがに不安に思えて来た。
ある日のこと、ついに母さんが姉さんから縫いぐるみを取り上げようとした。
フネ『サザエや、もういい加減にしたらどうだい』
サザエ『え、何が?母さん』
フネ『これは……』グイッ
サザエ『ああっ、駄目よそんなに乱暴にタラちゃんを引っ張っちゃ!』
フネ『これはタラちゃんなんかじゃないのよ……』
サザエ『あ、ああ……』
フネ『分かってくれたかい?』
サザエ『ほら母さん、タラちゃんが痛がってる!離してあげて!』
フネ『サザエ……』
サザエ『大丈夫?タラちゃん』
姉さんはすっかり縫いぐるみをタラちゃんだと思い込んでいたのだ。
その件以来母さんは姉さんのことには触れないようになってしまったし、
他の家族も、もっと時間が経てば、元に戻るだろうと楽観的に考えていた。
それにどうしようも無かったのだ。
父さんと母さんは古い人で、姉さんを精神科に連れていくことを決断しかねていた。
マスオ兄さんも我が子を失った悲しみは深く、自分以上に傷ついている妻を狂人扱いすることは出来なかったのだ。
そうして今に至る訳だが、一年近く使われ続けている縫いぐるみは所々ガタが出てきている。
ワカメや母さんが、姉さんの目の届かない所で直しているのだが、いずれ限界がくるだろう。
カツオ「それ、まだ大丈夫そうかい?」
ワカメは頭部に綿を詰め足しながら曖昧に頷いた。
ワカ「うーん、そろそろ危ないかもしれないわね」
薄汚れた縫いぐるみがワカメの手の中でグラグラと揺れている。
綿を詰め終わり、開いた部分を針と糸で縫い合わせるワカメの手元を僕はぼーっと眺めていた。
何度もやっている作業のため、スムーズに動く針の動きに見とれていると不意に首筋に視線を感じたような気がした。
カツオ「……誰?」
僕は勢いよく振り向く。
瞬間、ぴしゃりと襖が閉められた。
それを開いて後を追い掛ける勇気は僕には無かった。
ワカメ「どうしたの……?」
カツオ「あ、ああ……誰かが覗いてたみたいだったからさ」
ワカメ「・・・・・・もしかして……!」
カツオ「大丈夫だって……それは、ない……よ」
そんな根拠はどこにもないのだけれど僕は掠れる声で呟いた。
カツオ「姉さんの訳……ないじゃないか、はは」
やがて母さんの声に呼ばれ、僕とワカメは夕食の席に着いた。
カツオ「さ、さあタラちゃん、姉さんの所に行きなよ」
僕は姉さんの隣に縫いぐるみを置く。
先程のあれは本当に姉さんでは無かったのだろうか。
もし部屋を覗いていたとしたらワカメが縫いぐるみを修理していたのを見ていたかもしれない。
姉さんにとってこの縫いぐるみはタラちゃんなのだ、その体を開き、針を刺す場面などどのように映るだろう。
サザエ「さあタラちゃんいらっしゃい、おいしそうなハンバーグでしょう」
僕は笑顔で縫いぐるみを抱き抱える姉さんに、心の中で安堵のため息をついた。
サザエ「はい、タラちゃんあーんして。おいしい?そう、うふふ」
サザエ「あらー駄目じゃないこんなにこぼしちゃって……タラちゃんもそろそろ一人で食べられるようにならなきゃ駄目よ」
食卓では姉さんの楽しそうな声が響く。
縫いぐるみは口に押し付けられた食べ物をただボロボロと床に落とすばかり。
最近ではすっかり見慣れた我が家の食事風景だ。
サザエ「あら?どうしたのタラちゃん・・・もう食べないの?食欲がないってどうしたのよ。頭が痛いの?うーん、風邪かしら?少しお部屋で横になりましょうか、そうね、それがいいわ・・・母さん、私タラちゃんを休ませて来るわね」
姉さんから心配そうな言葉が続く、どうやら縫いぐるみの具合がよくないらしいのだ。
フネ「あ、ああ……そうかい」
姉さんは縫いぐるみを大事そうに抱き抱えると、寝室へと向かった。
僕らが食事を終えても、姉さんは戻らなかった。
皆特に気にもせずに、母さんとワカメは食器の片付け、父さんとマスオ兄さんは晩酌を始めていた。
することがなくなった僕は、部屋に戻って漫画でも読もうかと廊下へ歩き出した。
姉さん達の寝室の前を通過する時、妙な音が聞こえてきた。
思わず立ち止まり耳を済ませてみると、その音はどうやら人の囁き声のようだった。
止めておけばいいものを、僕は思わずその場に立ち止まり、耳を済ました。
サザエ「……大丈夫よ、タラちゃん……大丈夫だからね」
どうやら姉さんがタラちゃんを気遣う言葉をかけているようだった。
どこか抑揚を無くしたようなその声に、僕は少しだけ違和感を覚える。
サザエ「大丈夫だからね、すぐに良くなるわよ、すぐに……」
僕頭のの中には、姉さんがタラちゃんに添い寝をしてあげている微笑ましい光景が浮かぶ、ほんの二年前には当たり前だったその光景。
サザエ「ほらね、こうやって悪い所を……」
頭が痛いと言っていたから、撫でてあげているのだろうか。
たとえ全てが姉さんの頭の中で作られた話であっても、当たり前な親子の会話が部屋の中で交わされている。
だけど次の瞬間、頭に浮かんだ微笑ましい親子の図は音もなく崩れさった。
サザエ「痛いところ全部……とってあげるからね」
プチプチと何かを引き契るような音が聞こえてきた。
とってあげる、とはいったいなんのことだろう。
縫いぐるみを我が子と思い込んでいるはずの姉さんが、いったいなにをしているのか。
僕の頭の中で警報がなる、早くこの場を離れろ、と。
さもなくば見てはいけないものを見てしまうぞ、と。だけど僕はその場から動けなかった。
サザエ「ほら……これが悪いのよ。悪い物を詰められて……痛かったでしょう?」
サザエ「可愛いタラちゃんに針を刺して……こんなことを……可哀相に……可哀相に……うっうぅ……」
見られていたのだ。
ワカメが縫いぐるみを直していたところも全部。
僕の背中に、凍り付いてしまったのかのような嫌な感覚が広がった。
サザエ「うっううぅう……」
部屋の中からは姉さんの嗚咽の混じった声が聞こえてくる。
僕は相変わらず一歩も動けないままに、部屋の襖を凝視していた。
その時、不意に肩を叩かれ僕はヒッと情けない、声にもならないような短い悲鳴を漏らした。
ワカメ「お兄ちゃん?何やってるのよ、こんなところで」
カツオ「ワ、ワ、ワカメ……」
いつもの調子で話し掛けてくるワカメに、僕は震える声でようやく答えた。
頭の中では姉さんに気づかれてしまったのではないかということでいっぱいで、一秒でも早くこの場から立ち去りたかった。
ワカメ「母さんにこれを姉さんの部屋にって頼まれたのよ」
ワカメの手の中には水とお粥の乗った盆があった。
母さんが、姉さんに縫いぐるみに食べさせるように、と作ったものだろう。
ワカメ「そこ、開けてお兄ちゃん」
カツオ「……」
僕は瞬時に返事を返すことが出来なかった。
ワカメはまだ知らない、姉さんがさっき僕らの部屋を覗いていたということを。
この部屋の中で起きているであろう事を。
開けてはいけない、そんな予感が頭に渦巻く。
だけどいつの間にか止まっていた姉さんの嗚咽に、先程の声の現実感が薄らいでいた。
中にいるのは僕の姉さんだ、それは紛れも無い真実。
姉さんの部屋の襖を開けることにどんな危険があるものか。
僕は、静かに襖を横に引いた。
ワカメ「姉さーん!こ、……」
一歩先に部屋へ踏み出したワカメ、その足が止まった。
カツオ「ワカメ?」
僕は固まってしまった妹を押しのけるように姉さんの部屋を覗きこむ。
カツオ「姉さん……?」
ワカメ「いやあぁあああ!」
ワカメは悲鳴を上げると手に持っていた盆をひっくり返しながら、その場から走り去った。
僕は何も反応することが出来ずに、姉さんの事をただ眺めていた。
部屋中に散乱する白い綿。
縫いぐるみにぎゅうぎゅうに詰められていたそれを全て引きずり出したようだ。
抜け殻のようになった布を抱きしめた姉さんが虚ろな目でこちらを眺めていた。
サザエ「……」
なにやら懸命に口を動かす姉さんに、始めは何かを話しているのかと思ったけれど、違ったようだ。
中身の抜けた縫いぐるみを持ったのとは逆の手を口許に運ぶ、その手には綿が一掴み握られていた。
姉さんはそれを食べていたのだ。
サザエ「……」
僕は状況を理解するのに少し時間がかかった。
その間にも姉さんは何度か手を動かし、口いっぱいに綿を詰め込む。
サザエ「うっうううぐっ」
カツオ「姉さん!」
姉さんの苦しそうな声に僕はようやく動くことが出来た。
カツオ「何やってるんだよ……!」
僕は姉さんの口に手を突っ込むと、中の物を掻き出そうとした。
カツオ「なんでこんな……窒息しちゃうよ!!」
姉さんは綿を次々に飲み込んでいたようで、僕はそれを吐かせなくては、と
片方の手で背中を叩き、もう片方の手の指を喉の奥へと押し込んだ。
サザエ「うあえっえおぉ」
カツオ「痛いっ!!」
姉さんは苦しかったのか、僕の指の付け根を強く噛んだ。
僕は痛さに指を引いたけど、噛み付く力が強すぎて抜けない。
サザエ「ふうぅうう、ふうぅううぅ」
姉さんは荒い呼吸を繰り返している。
僕は空いている方の手でその背中をさすった。
噛み付かれた手は姉さんの口の中で血を流しているようで、指を伝い赤いものが見える。
フネ「サザエッ!?な、な、なんだいこれは……」
ワカメが呼んだのだろう、母さんが部屋に入ってきた。
一瞬動揺したようだが、気丈な彼女はすぐに状況を把握し、僕らの側に座る。
フネ「サザエ、サザエわかるかい?ほら、カツオの手を離しておやり」
サザエ「うぅう……」
母さんの言葉が届いたのか、一瞬顎の力が弱まった。
その隙に僕は手を抜いた。
かみ砕かれ無かったのは幸いだけど、指の根本には引き裂かれたような傷がついていた。
鋭利な刃物でつけられた傷よりも、そうでない物で切られた方が酷い怪我になるという。
この傷はしばらく残りそうだ。
フネ「ほらゆっくり口の中のものを出しなさい、苦しいでしょう」
サザエ「うあぉお」
姉さんは母さんに背中をさすられながら、口の中の綿を吐き出していく。
僕の血で染まった綿は、まるで真っ赤な髪の毛のようにみえた。
サザエ「あぁあっ……たらちゃ……が」
フネ「サザエ、これはタラちゃんじゃないんだよ……」
サザエ「ううぅうああぁあ」
姉さんは母さんの膝に顔を埋めるようにして泣いていた。
次の日、何もかも元通りになったかのようだった。
母さんと姉さんはいつも通り二人で並んで朝食の支度をしていたし、笑い声も響いていた。
ただ、そこにはもう縫いぐるみはなかった。
ワカメは昨日の出来事がショックだったのか口数が少なかったが、明るく笑う姉さんを眺める視線に暗いものはなく、学校に行く時間にはいつもの彼女に戻っていた。
縫いぐるみをタラちゃんと呼んでいた姉さんは以前と変わらないようでいて、やはりどこか異様だった。
だけど今朝の姉さんは昨日までの姉さんとは雰囲気が違っている。
きっと姉さんもタラちゃんを失ったショックから立ち直り、現実を受け入れられるようになったのだ、僕はそう思っていた。
カツオ「ただいまー」
学校は何事もなく終わり、僕は家に帰って来た。
台所では姉さんが昨日のハンバーグで使った残りであろうひき肉をこねていた。
母さんは買い物にでもいったのか、ワカメはまだ帰っていないのか、二人とも姿が見えなかった。
僕は別段気にも止めずに、駆け足で部屋へと向かう。
中嶋たちが野球をするためにいつもの公園で待っているのだ。
昨日の姉さんに噛まれた傷口も、巻かれた包帯こそ痛々しいが、痛みはすっかり引いていた。
僕は早く出掛けたいために、はやる気持ちを抑え切れずに机の上にランドセルを放り投げた。
衝撃でランドセルの中身が散らばるが、気にしてはいられない。
カツオ「いってきまーす!」
靴を履く時間ももどかしく、僕は公園へと走りだした。
だけどしばらく走った後、バットとグローブを忘れて来たことに気がつき、僕は元来た道を引き返すことになった。
カツオ「お、ワカメも帰ってきたのか」
入れ違いになったのだろう、僕が玄関に戻るとワカメの靴が揃えて置かれていた。
カツオ「……姉さんはどうしたんだろう」
さっきは台所にいたはずの姉さんがいない。
だけど早く野球に行きたい僕は特に気にも止めずに自分の部屋へと急いだ。
カツオ「あれ」
てっきり部屋にはワカメがいるものだと思っていた僕は、だれもいないことに拍子抜けしてしまった。
姉さんの部屋にでもいったのか。
カツオ「姉さんの……部屋」
僕は昨日の出来事を思い出し、少しだけ顔をしかめた。
何故だか胸騒ぎがする。
だけど机の上にぶちまけられたかばんの中身に目をやると、そちらに気を取られて勘違いのような不安なんて吹き飛んでしまった。
カツオ「これは……まずいまずい、テストの答案がまる見えだ」
今日返された限りなくゼロに近い数字がかかれた紙切れを僕は慌てて拾いあげる。
こんなものが姉さんに見られたら大目玉だ。
その答案用紙も含め、散らばった荷物をそのままかばんに詰め直し、僕は目的のバットとグローブに手を伸ばす。
その時、廊下の方から物音が聞こえた。
ズル……ズル……と何かを引きずるような音。
そして言葉までは聞き取れないが、何かをぶつぶつと呟くような声。
カツオ「姉さん……?」
僕は何故かその音の正体を確かめることが出来なかった。
襖を開け、廊下に出てしまうのは簡単なのに、どうしても足が進んでくれない。
カツオ「こっちに来てる……?」
その場に動けないでいるうちに、姉さんの声は確実に近づいてきているのがわかる。
昨日姉さんの部屋の前で感じた、警告音のような嫌な感覚が全身に広がる。
姉さんはいったい何をしているのか確かめたい。
この場から逃げ出してしまいたい。
確かめなくては。
逃げなくては。
二つの感情が僕の頭の中で渦巻いて結論が出ない。
逃げようと思えば窓からでも逃げられるのだし、確かめるのには廊下に出てしまえばいいのだ。
だけど僕はそのどちらも選ばず、部屋の中に留まることにした。
押し入れの中に身を隠し、息を潜める。
姉さんがこの部屋に入るとは限らないが、もしもの場合にいきなり鉢合わせてしまう事態を避けるためだ。
押し入れに入ってしまうと謎の音も姉さんの声も聞こえない。
押し入れの襖の模様に紛れるように空けた小さな穴から外を伺う。
そこにはただの日常が広がっていた。
なんの変哲もない僕とワカメの部屋だ。
ただ布団に圧迫されるように押し入れに隠れている僕が息苦しい思いをしているだけだ。
しばらくそうしていたが、姉さんが入って来るわけでもワカメが入って来るわけでもなく、時間だけが過ぎた。
先程僕が感じた危機感のようなものなんて、とうの昔に薄れて消え去って、
なんだか隠れているのが馬鹿馬鹿しく思えてきた。
もうやめよう、気のせいだったのだ。
だって今朝の姉さんはあんなに明るくて、笑顔だった。
口うるさくてお節介な僕の姉さん、ただそれだけなのに、僕はなんで隠れていなければならないのか。
カツオ「……出よう」
そう思い押し入れを開けようと手を掛けた瞬間、廊下と僕の部屋を繋ぐ襖が開かれた。
べちゃり、そんな音を立てて、何かが投げ込まれる。
それがいったいなんなのか僕にはなかなかわからなかった。
サザエ「あれー?カツオは帰って来てたんじゃなかったのかしら?」
真っ赤で、同じ色の液体を滴らせるそれはワカメの服を着ていた。
サザエ「おかしいわねー、一回出てってまた戻ってきたと思ったのに……」
言葉だけ聞けばいつもの姉さんとなんら変わりはないように思えるが、感情の篭らない声と虚ろな瞳は
まるで昨日の姉さんのようだった。
姉さんの服や顔に飛び散った赤い液体と、ワカメの服を着た物を染めるその色が、
誰かの血の色なのだと気づくにはしばらく時間がかかった。
誰か、なんて信じたくはないし信じられるようなことではないけれど、
そこに転がっている赤い塊はワカメで、流れている血は彼女の物なのだ。
服から出ている部分は原形を留めない程にぐちゃぐちゃと何かに切り刻まれたかのような
状態なのに、真っ赤に染まった服をそれでも着こなしているのはどこかシュールな光景だった。
突然のことで麻痺した恐怖心が僕に悲鳴を上げさせようとしている。
それを口に手を押し込み堪えた。
くしくもそれは昨日姉さんに噛まれた方の手で、傷口に僅かに走る痛みが僕の思考をなんとかつなぎ止めていた。
サザエ「ちょうどいいところに帰って来てくれたと思ったのに、勘違いだったみたいね」
何がちょうどいいのかはわからないけど、姉さんの手に握られた包丁をみるかぎり
僕にとってはちょうど良くないことに違いない。
おまけに反対側の手にはあのタラちゃんの縫いぐるみが抱かれていた。
サザエ「ごめんね、タラちゃんもう少し我慢してね」
姉さんはまた縫いぐるみに話し掛け、本当の我が子にするように笑いかけた。
不思議なのは昨日綿を抜かれてぺしゃんこになっていたはずのそれが、いまは妙に膨らんで見えたことだ。
サザエ「昨日のタラちゃんはタラちゃんじゃなかったのよ。だって母さんもそう言ってたしね・・・中身があんなに軽くてふわふわしていたもの。もう一度ママの体に戻そうと思っていたけど、もっと簡単に出来るって気がついたのよ・・・タラちゃんの体を取り返せばいいんじゃない。」
姉さんのぶつぶつと呟く声が耳に届く。
言っている内容はめちゃくちゃなのだが、今の姉さんに見つかることは非常に危険だということは分かった。
無惨なワカメの姿を見ても、可哀相だとか酷いだとかの感情が浮かぶのではなく、ただ恐怖だけが僕を捕らえている。
サザエ「きっとワカメがタラちゃんをこんな目に合わせたのよ、体を奪って綿と詰め換えていたのよ」
だからワカメから取り返したのだろう。
ワカメの体から肉を削り取り、縫いぐるみに詰めていたようだ。
縫いぐるみから滴る血も全部ワカメのものだったのだ。
サザエ「でもワカメからばっかりじゃ可哀相よね、カツオだって悪いんだもの」
僕の名前があの声で呼ばれたとき、思わず体が強張った。
どこかで音を立ててしまっていないか、速まった心拍と同じリズムで手の傷がドクドクと脈打った。
サザエ「タラちゃんが酷い目に合わされているってのに黙って見てるだけなんて」
サザエ「ワカメはこれで許して上げる、体が軽くなりすぎちゃったでしょう」
サザエ「台所にお肉を用意しておいたから足りない部分に足すといいわよ」
姉さんは動かないワカメを揺さぶりながらそんなことを言っていた。
ワカメはきっともう死んでいるはずだ、あの状態ならば生きている方が悲惨なようなのだ。
口の端を微かに歪めて笑う姉さんだけが楽しそうにみえる。
姉さんは虚ろな視線をフラフラと漂わせて、ある一点で止めた。
サザエ「あら、やっぱりカツオ、帰って来ていたのね」
僕は一瞬見つかったのかと思った。
だけどそれは単なるはやとちりで、姉さんが見つめていたのは僕の机の上だった。
サザエ「さっきは中身が散らばっていたのに……きれいにしまわれてる」
いつ見たのだろう、僕が一度目に帰宅してから次に戻ってくるまでの間に違いないだろうが、
その時にはワカメはどうしていたのだろうか、すでに姉さんに肉を削がれた後だったのだろうか。
それを考えると胸が裂けそうな思いで苦しかったが、妹の悲惨な最期を哀れむ余裕など今の僕にはないのだ。
サザエ「まだ家のどこかにいるのかしら、ちょっと探してくるからここにいてねタラちゃん」
べしゃりと音を立ててワカメだったものの上に、肉の詰まった縫いぐるみが置かれた。
もしも姉さんに見つかってしまえばあれらの仲間入りだ。
それは絶対に避けなければいけない。
ワカメを切った時に刃毀れしたのであろう包丁は、傾き掛けた太陽の光で凸凹とした刃先を浮かび上がらせている。
それを手にした姉さんがくるりと後ろを振り向きこの部屋からでていくそぶりをした瞬間、僕は安堵のため息を漏らした。
それが、いけなかった。
これが走馬灯というものなのか、様々な光景が頭に浮かんで消える。
こんなときだからなのか、みんなの笑顔や楽しかった思い出ばかりが出てくる。
そういえば母さんは町内の婦人会で今日は遅いって言っていたな、とか
中嶋たちは僕が行かなくても野球をしているんだろうな、とか
今の僕には遠い世界の話のような言葉が浮かび、目の前の暗闇が裂けた。
サザエ「タラちゃん、今できるからね」
その声の聞こえた後、赤黒く染まった刃先が僕を―・・・